この記事のポイント
・悪意の遺棄(あくいのいき)とは、「夫婦が同居して、互いに協力し扶助する義務」を正当な理由なく意図して果たさないこと
・悪意の遺棄が認められるには、積極的に夫婦生活を破綻させる意図があることが必要
・悪意の遺棄を理由に慰謝料請求や離婚が認められる可能性がある
「夫が突然家出して、生活費を送ってくれず困っている…」
そのような場合、「悪意の遺棄」を理由に慰謝料を請求できるかもしれません。
夫婦はお互いに同居し、協力する義務がありますが、一方的な別居はその義務に反しており、悪意の遺棄という不法行為が成立する可能性があるからです。
また、悪意の遺棄は法定離婚事由の1つであるため、裁判で離婚を請求することもできます。
このコラムでは、悪意の遺棄が認められた裁判例、悪意の遺棄で離婚や慰謝料を請求できるのか、などについて弁護士が解説します。
悪意の遺棄とは
悪意の遺棄(あくいのいき)とは、「夫婦が同居して、互いに協力し扶助する義務」を正当な理由なく意図して履行しないことであり、法定離婚事由のうちの1つです(民法第770条1項2号)。
過去の裁判例では、以下のように定義されています。
社会的倫理的非難に値するような、婚姻共同生活を廃絶する意図を有して(またはそれを容認して)、正当な理由なく同居協力扶助義務を継続的に履行せず、共同生活の維持を拒否すること

民法上、夫婦は同居して互いに協力し、扶助する義務があります(民法第752条)。
そのため正当な理由なく、夫婦がこの同居義務や協力扶助義務をはたさなければ、悪意の遺棄となる可能性があるのです。
ただし、単身赴任や、親の介護や子どもの通学のための別居、夫婦が同意したうえでの別居などは、正当な理由があるため、通常は同居義務・協力扶助義務違反にはなりません。
配偶者による悪意の遺棄が認められた場合、配偶者が離婚に合意しなかったとしても、最終的には裁判で離婚できる可能性が高いです。
なお、裁判で離婚が認められる「法定離婚事由」には、以下のようなものがあります。
<法定離婚事由>
• 不貞行為
• 悪意の遺棄
• 3年以上の生死不明
• 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないこと
• その他婚姻を継続し難い重大な事由
詳しくは「離婚に必要な5つの理由」をご覧ください。
悪意の遺棄の具体例
それではどのような場合に、悪意の遺棄があったと認められるのでしょうか。
当事者の意図や、客観的な言動などさまざまな事情が考慮されるため、一概にはいえませんが、次のような事情があれば、悪意の遺棄が認められる可能性があります。
- 正当な理由もなく一方的に家を出て行き同居を拒否し、病気の配偶者を置き去りにし、長期間生活費を送らない
- 配偶者を家から追い出したり、家にいられない状況にして追い出して帰宅を拒否したりして同居義務を果たさない
- 別居して不貞相手と長期間同棲し、夫婦関係修復は困難で生活費を送らない
- 別居時期も行先も連絡せず、一方的に別居し、将来の相談も一切しない
次に、悪意の遺棄が認められた裁判例と認められなかった裁判例をそれぞれ紹介します。
(1)悪意の遺棄が認められた裁判例
【1.東京地方裁判所判決平成28年3月31日】
<事例>
妻が、夫に対して、不貞行為、悪意の遺棄、肉体的精神的暴力および子の奪取を理由として、不法行為に基づく損害賠償請求として、慰謝料計300万円を請求した。
妻は、一緒に生活をやり直すよう伝えていたにもかかわらず、夫がこれを無視して不貞関係を続けるために妻を置き去りにして別居したとして、夫による悪意の遺棄を主張した。
<裁判所の判断>
夫は、不貞相手との交際を主たる目的として、妻が関係修復を希望しているにもかかわらず、一方的に別居に踏み切り、その後も生活費の負担などの夫婦間の協力義務を果たしていないのであるから、被告による別居は、悪意の遺棄として、不法行為が成立するとした(悪意の遺棄の慰謝料は50万円)。慰謝料合計額は180万円。
【2.浦和地方裁判所判決昭和60年11月29日】
<事例>
妻が、夫に対して、不貞行為および悪意の遺棄を理由として離婚、財産分与などを請求した。
<裁判所の判断>
夫は、半身不随の身体障害者で日常生活もままならない妻を自宅に置き去りにし、正当な理由なく長期間別居を続け、その間生活費もまったく送金していないものであり、悪意の遺棄であり、法定の離婚事由があるとして離婚を認めた。
【3.東京地方裁判所判決平成21年4月27日】
<事例>
元妻が、元夫に対して、不貞行為や悪意の遺棄などにより離婚するに至ったとして、不法行為に基づく損害賠償として慰謝料1,000万円を請求した。
<裁判所の判断>
元夫は、経済的に献身的に支えてくれた元妻と生まれて間がない子を置いて家を出て、その後夫婦関係の修復を図ることなく、かえって離婚を求めて調停を申し立てたり、調停で決まった養育費の支払いを滞らせたりするなどし、離婚に至るまで帰宅しなかったのであるから、悪意の遺棄に該当し、不法行為が成立するとした(慰謝料300万円。不貞行為は証拠不十分で認めず)。
(2)悪意の遺棄が認められなかった裁判例
悪意の遺棄は、単なる一方的な別居では足りず、社会的倫理的非難に値する、婚姻共同生活の廃絶を意図していることが必要と考えられています。
裁判になれば、悪意の遺棄を主張する側が、上記の意図などを証拠に基づいて立証する必要があるため、立証のハードルが高く、悪意の遺棄を認める裁判例は少ない傾向にあります。
ただし、複数の法定離婚事由を主張して離婚を求めることが一般的です。そのため、悪意の遺棄が認められなくても、婚姻を継続し難い重大な事由があるとして離婚が認められるケースも少なくありません。
【大阪地方裁判所判決昭和43年6月27日】
<事例>
妻が、夫に対して悪意の遺棄などを主張して離婚および財産分与を請求した。
<裁判所の判断>
夫が、たとえ仕事のためとはいえあまりに多い出張や外泊を繰り返し、妻子を顧みない行動について、同居協力扶助の義務を十分に尽くしてはいないが、悪意の遺棄に該当するとまではいえないとした。
しかしながら婚姻を継続し難い重大な事由はあるとして、離婚を認めた。

「悪意の遺棄」までは認められないとしても、別居に至るさまざまな事情を考慮した結果、「婚姻を継続し難い重大な事由」が認められ、離婚自体は認められることがあります!
悪意の遺棄の判断における注意点とは
配偶者の行為に悪意の遺棄が認められるかどうかを判断する際は、次のような点にご注意ください。
(1)夫婦関係が破綻することを認識している(または認容している)ことが必要
「悪意の遺棄」なので、単なる遺棄(正当な理由なく、夫婦の同居義務・協力扶助義務を果たさないこと)では足りず、悪意が必要となります。
ここでいう「悪意」とは、社会的倫理的非難に値する要素を含むものであって、積極的に婚姻共同生活の継続を廃絶するという結果の発生を企図し、もしくはこれを認容する意思のことを指します。
つまり、遺棄をした配偶者に、積極的に夫婦生活を破綻させる意図や、少なくともこれをよしとする意思が認められる必要があるでしょう。
このような意思の存在は、悪意の遺棄があったと主張する側が証拠をもって証明しなければなりません。
証拠としては、次のようなものが考えられます。
- 一方的に別居したことがわかるメール、SNSのやり取り、録音など
- 配偶者が離婚を希望していることがわかるメール、SNSのやり取り、録音など
- 別居後生活費の振り込みがないことがわかる通帳
- 別居の原因が不貞行為であれば、不貞相手との肉体関係がわかるメール、写真、動画、録音など
(2)単に家事育児をしないだけでは認められない
同居しているけれども、配偶者が家事や育児に協力しない状況は、形式的には夫婦の協力扶助義務を果たしていないように感じられます。
しかし、単に配偶者が家事育児に協力しないという事実だけで、裁判所が悪意の遺棄を認めることはないでしょう。
それだけで、積極的に夫婦生活の破綻を意図または認容しているとまで判断するのは難しいためです。
形式上は同居していても、特段の事情がないのに生活費の負担をせず、配偶者としての関係維持も放棄するなどの事情(性交拒否・無視するなど)があれば、悪意の遺棄にあたるとする考え方もあります。
しかし、裁判所で悪意の遺棄が認められる可能性は低いでしょう。
したがって、このような場合には、悪意の遺棄に加えて、婚姻を継続し難い重大な事由があるとして、離婚を請求することをおすすめします。
(3)さまざまな事情が総合的に考慮される
裁判所による悪意の遺棄に該当するかどうかは、たとえば次のような状況を総合的に考慮して判断されます。
- 婚姻からその状況に至った経緯
- 生活費負担の状況
- 夫婦の関係性
- 別居後の生活の窮状
- 子どもの有無
したがって、事前に配偶者の行為が悪意の遺棄に該当するかどうかを判断することは簡単ではありません。
悪意の遺棄をされた場合の対処法
配偶者に突然別居された場合に取るべき対処法を説明します。
まずは、当事者で話し合って問題解決を目指します。
その際には、忘れずに婚姻費用(生活費)の分担の話もするようにしましょう。
話し合っても問題を解決できない場合には、家庭裁判所に次のような調停を申し立てて、調停委員の仲介のもと話合いで解決を目指すことができます。
特に、婚姻費用は、過去の未払い分をさかのぼって請求することはできないと考えられているため、支払いが滞ったらすみやかに調停を申し立てるようにしましょう。
| 請求する内容 | 申し立てる調停の種類 |
|---|---|
| 婚姻費用(生活費)の請求の場合 | 婚姻費用分担請求調停 |
| 夫婦関係の問題解決を求める場合 | 夫婦関係調整調停(円満) |
| 離婚を求める場合 | 夫婦関係調整調停(離婚) |
詳しくは「婚姻費用分担請求(離婚問題の知識と法律)」もご覧ください。
悪意の遺棄を理由として離婚できるのか
配偶者が離婚に同意すれば、理由を問わず離婚することができます。
しかし、配偶者が離婚を拒否した場合、裁判で離婚が認められるためには法定離婚事由が必要です。
悪意の遺棄は法定離婚事由の1つなので、裁判所が悪意の遺棄があったと認めれば、最終的に離婚できる可能性が高いでしょう。
しかし、裁判所が悪意の遺棄を認めるケースは少ないため、裁判で離婚を請求する場合には、悪意の遺棄のほかに、不貞行為や婚姻を継続し難い重大な事由の存在を主張・立証することが一般的です。
悪意の遺棄で慰謝料請求する際の注意点
悪意の遺棄は民法上の不法行為に該当するため(民法第709条)、不法行為により受けた精神的苦痛に対する損害賠償として慰謝料を請求できます。
ただし、請求の際にいくつか注意すべき点があるため、見ていきましょう。
(1)悪意の遺棄の証拠が必要
悪意の遺棄が不法行為に該当するとして慰謝料を請求する場合、悪意の遺棄の事実については、請求をする側が証拠によって証明する必要があります。
相手方が「たしかに悪意の遺棄をした。悪かったから慰謝料を支払う」と認めれば、証拠がなくても慰謝料請求は可能です。しかし、通常はそのような返答を期待できないため、請求する前に証拠を確保しなければなりません。
悪意の遺棄の証拠としては、次のようなものがあります。
- 生活費が振り込まれなくなった通帳
- 悪意の遺棄の状況がわかる日記や家計簿
- 別居の事実がわかる住民票や賃貸借契約書
- 一方的な別居の経緯がわかるメールややり取り
- 夫婦関係の修復を求めたのに拒否された経緯がわかるメールのやり取り
- 離婚を求められたら、それがわかるメールのやり取り
- 別居の原因が不貞行為であれば、肉体関係がわかる証拠(動画、写真、メールなど)
- 配偶者の浪費や借金がわかるクレジットカード利用明細やキャッシング明細書など

どれか1つあれば悪意の遺棄が認められるわけではなく、複数の証拠を組み合わせることで、悪意の遺棄に該当する行為があったことを段階的に証明しようとすることが多いです。
(2)請求には時効がある
慰謝料の請求は、いつまでも請求できるものではなく、法律上、一定期間が経過すると請求できなくなります。
慰謝料を請求したいと考えている場合には、この期間内に請求するようにしましょう。
消滅時効の期間は、次の2つです(民法第724条)。
- 被害者が損害および加害者を知ったときから3年間
- 不法行為のときから20年間
上記期間のうち早く訪れたほうが経過した時点で、慰謝料を請求する権利は時効で消滅してしまいます。
また、悪意の遺棄が原因で離婚せざるを得なかったことを理由として慰謝料を請求する場合、時効期間は離婚成立から3年です。
正確には、時効期間が経過していても、慰謝料の請求自体は可能で、法律上何ら問題はありません。
つまり、相手が「時効期間が経過しているから支払わない」と主張しない限り、考慮されないのです。
したがって、相手方が消滅時効を主張せず、自主的に支払いに応じるのであれば、慰謝料を受け取れます。
(3)離婚しない場合には婚姻費用の請求が現実的
すぐに離婚しない場合、悪意の遺棄を理由とした慰謝料請求よりも、毎月しっかりと婚姻費用(生活費)を支払ってもらったほうが、長期的に見てメリットが大きいと考えられます。
悪意の遺棄は証拠で証明することが難しいのに対して、婚姻費用の請求は、基本的に結婚している事実と婚姻費用が支払われていないことを証明すればよいためです。
また、婚姻費用は、通常、調停を申し立てたときまたは配達証明付きの内容証明郵便で婚姻費用を請求したときから、同居再開または離婚成まで受け取ることができます。
したがって、婚姻費用を請求しても支払ってもらえない場合には、すみやかに婚姻費用の分担請求調停を申し立てたり、配達証明付きの内容証明郵便で婚姻費用を請求したりするようにしましょう。
調停で話合いが決裂して調停不成立となっても、審判に移行し、裁判所が適切な婚姻費用額を審判で定めてくれます。
参考:婚姻費用の分担請求調停|裁判所
【まとめ】悪意の遺棄が認められなくても、離婚が認められることはある!
法定離婚事由である悪意の遺棄が認められるには、積極的に夫婦生活を破綻させる意図や、少なくともこれを認容する意思が必要だと考えられています。
また、裁判所が悪意の遺棄を認めたケースは少ないため、事前に判断することは困難でしょう。
そのため、悪意の遺棄を理由に離婚できるかお悩みの場合は、弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士であれば、さまざまな事情を考慮したうえで適切な見通しを立て、ほかの離婚事由も主張すべきかどうか、証拠が十分かなどについてもアドバイスできます。
配偶者の行為が悪意の遺棄ではないかと感じ、離婚でお悩みの方は、まずは弁護士にご相談ください。
アディーレでは、京都府内のさまざまな地域にお住まいの方から、お問合せいただいております。
京都にお住まいの方で、離婚に関するご相談はアディーレへ。
【対応エリア】京都市北区・上京区・左京区・中京区・東山区・下京区・南区・右京区・伏見区・山科区・西京区、福知山市、舞鶴市、綾部市、宇治市、宮津市、亀岡市、城陽市、向日市、長岡京市、八幡市、京田辺市、京丹後市、南丹市、木津川市など




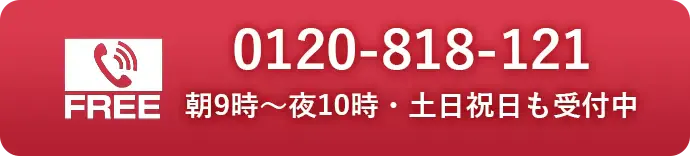
どのようなことに関しても,最初の一歩を踏み出すには,すこし勇気が要ります。それが法律問題であれば,なおさらです。また,法律事務所や弁護士というと,何となく近寄りがたいと感じる方も少なくないと思います。私も,弁護士になる前はそうでした。しかし,法律事務所とかかわりをもつこと,弁護士に相談することに対して,身構える必要はまったくありません。緊張や遠慮もなさらないでくださいね。「こんなことを聞いたら恥ずかしいんじゃないか」などと心配することもありません。等身大のご自分のままで大丈夫です。私も気取らずに,皆さまの問題の解決に向けて,精一杯取り組みます。