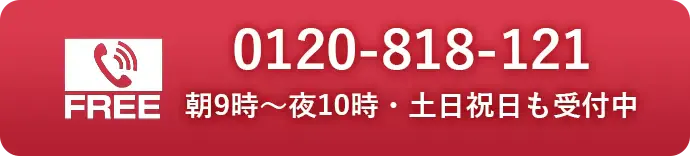- 妊娠中に交通事故に遭ってしまったのですが、示談交渉などで不利になることはありますか?
-
妊娠中はMRI検査をすることができませんので、事故によるケガの症状の原因を証明する手立てがない、ということもあり得ます。その場合には、後遺障害の等級認定申請や示談交渉で不利になるというデメリットが生じることもあります。
- 妊娠中に交通事故にあいました。胎児・新生児に影響があった場合、その損害は補償されますか?
-
胎児である間に受けた不法行為によって、出生後に障害が生じ、後遺障害が残存した場合には、加害者に対してそれらについての損害賠償請求をすることができます(民法721条、最高裁平成18年3月28日判決)。
したがって、胎児が障害をもって産まれてきた原因が、交通事故(不法行為)にあるのであれば、事故の加害者に、その分の損害を賠償するよう請求できます。
- 職業がモデルであるため、14級(腰部)が認定されていても逸失利益は払わないと保険会社にいわれました。逸失利益を請求することはできないのでしょうか?
-
加害者側の保険会社が、さまざまな理由をつけて示談金額を抑えようとすることは頻繁に行われています。そのため、必ずしも保険会社の回答に合理的な理由があるとは限りません。
今回のケースでも、認定等級14級(腰部)の後遺障害が、モデルのお仕事に影響を与えないとは限りませんので、一律に支払われないということはありません。その後遺障害がモデルのお仕事に影響するかどうかは、具体的な業務の内容によって判断されます。「モデルの仕事」と一口にいっても、レッスン、オーディション、打合せ、撮影、営業、デスクワーク等、その業務は細かく分けられます。そのため、細かく分類した業務ごとに、後遺障害14級(腰部)がどの程度影響を与えるかを、保険会社に具体的に説明し、逸失利益を請求すべきです。
- 死亡した私の夫は年金生活者でしたが、逸失利益を請求できるのでしょうか?
-
逸失利益(いっしつりえき)とは、 交通事故被害者が仮に生きていれば、得られたであろう利益のことをいいます。この場合の利益は、通常、所得収入になります。そして、年金生活者の年金収入も、逸失利益性が認められるかが問題となります。この点、老齢年金、障害年金は、判例上、逸失利益性が認められています。他方、遺族年金は、判例上、逸失利益性が認められていません。
よって、通常、年金生活者の年金収入は、老齢年金収入または障害年金収入等について認められるものと考えられます。年金生活者の逸失利益(年金収入)は、簡単なイメージで表現しますと、「年金収入(年収)」×「平均余命年数」になります。
なお、年金生活者の逸失利益は、年金収入だけにかぎられず、たとえば、年金生活者が家事従事者であった場合、家事従事者としての逸失利益も認められる場合がありますので、ご注意ください。
- 給与所得者の場合、逸失利益はどのように算出すればよいのでしょうか?
-
給与所得者の後遺症による逸失利益は、通常、「基礎収入×労働能力喪失率×中間利息控除係数」で計算します。
基礎収入について
原則として、事故前の収入を基準とします。給与所得者の収入額は、収入証明書または源泉徴収票を基にして算出します。
収入証明書を発行してもらえない等の何らかの事由により、収入を証明する資料を集めることができないときは、賃金センサスの第1巻第1表の男女労働者別平均給与額または年齢別平均給与額によって算出する場合もあります。現実の収入額が統計の平均給与額よりも低い場合には、平均賃金が得られる蓋然性がない限り、原則として現実の収入額を基礎として算定します。
将来の昇給については、公務員、大企業の従業員などのように給与規程、昇給基準が確立されている場合には考慮されます。なお、中小企業であっても将来昇給することが明らかであれば、昇給が認められる余地はあります。ただし、将来のベースアップについては、そのときの社会情勢や景気という要素が不確定で、予測し難いと否定される例が少なくありません。
労働能力喪失率について
労働能力喪失率とは、後遺障害によってどれくらい労働能力が失われたかという割合です。後遺障害の等級によって異なり、5~100%で設定されています。
中間利息控除係数について
「ライプニッツ係数」とも呼ばれ、将来にわたる損害賠償金を前倒しで受け取るために、賠償額を現在の価値に引き直すための係数です。
- 事業所得者の場合、逸失利益は、どのように算出すればよいのでしょうか?
-
個人事業主や農業従事者等で家族従業員を使用している場合には、事故前1年間の売上額から必要経費を控除した純益について、家族の寄与分を考慮した上で、被害者の寄与分を定め、それに応じた被害者本人の収入を算出します。
寄与分は、その事業者ごとに異なるため、その事業の規模、形態および関与者の状況を考慮して、具体的な割合を個別的に決定します。逸失期間の年数は、原則として就労可能年数を年収にかけ合わせ、中間利息を控除することで、計算をしていきます。
- 主婦(主夫)の場合、逸失利益はどのように算出すればよいのでしょうか?
-
主婦(主夫)の後遺症による逸失利益は、通常、「基礎収入×労働能力喪失率×中間利息控除係数」で計算します。
基礎収入について
収入のない主婦(主夫)の場合、基礎収入は原則として女性労働者の全年齢平均給与額(※)を用います。
女性労働者の全年齢平均給与額ではなく年齢別平均給与額をとるかについては確定されていませんが、東京・大阪・名古屋の各地裁交通部の取扱いについては、原則として全年齢平均給与額によります。パート収入等がある兼業主婦の場合で、現実収入額が統計の平均給与額より高い場合は、現実収入額を収入とします。パート収入等の現実収入額が統計による平均給与額より低い場合は、平均給与額を収入とします。
高齢の女性の場合であっても、余命年数、健康状態および家族関係を検討して、家事労働を行うことができる場合には、統計の平均給与額または相当程度に減額した額を収入額とします。※賃金センサスの第1巻第1表の産業や企業規模、学歴や性別、年齢別等で集計された平均年収の統計データ
労働能力喪失率について
労働能力喪失率とは、後遺障害によってどれくらい労働能力が失われたかという割合です。後遺障害の等級によって異なり、5~100%で設定されています。
中間利息控除係数について
「ライプニッツ係数」とも呼ばれ、将来にわたる損害賠償金を前倒しで受け取るために、賠償額を現在の価値に引き直すための係数です。
- 学生や幼児の場合、逸失利益は、認められないのでしょうか?
-
交通事故の被害者が、収入のない18歳未満の学生や幼児であっても、後遺障害等級が認定された場合には逸失利益が認められます。
逸失利益とは、交通事故によって後遺障害を負ったことにより失われた収入や利益のことです。後遺障害によって、仕事に就くことができない、もしくは就業できる職種や業務が制限されてしまうなどのハンディキャップを負い、収入の一部または全部が減額されてしまうことに対する補償を加害者側に請求できます。収入のない18歳未満の学生や幼児の逸失利益の計算については、基本的に、賃金センサスによる男女別全年齢平均賃金額を基礎とします。また、就労可能年数は、原則として18歳から67歳までの49年間を基礎として計算します。
- 無職の場合、逸失利益は、認められないのでしょうか?
-
無職者であっても、労働意欲・能力があり、就労の蓋然性がある場合には、賃金センサスの平均給与額や失業前の収入を基礎として逸失利益が認められる場合があります。
- 追突事故で車が破損したため自動車を修理に出しました。車両価格よりも修理代のほうが高いのですが、加害者に修理代の全額を負担してもらえますか?
-
修理費用が車両価格を上回っている状態を「経済的全損」といいます。事故車両が「経済的全損」と評価されると、被害者は車両の時価価格の限度でしか修理代の支払を受けることはできません。もっとも被害者は、事故直前の車両と同程度の車両を買い換えるために必要な諸費用については、これらも損害として請求することが可能です。
まずはお気軽にご相談ください。
朝9:00 ~ 夜10:00・土日祝日も受付中
0120-818-121